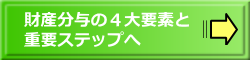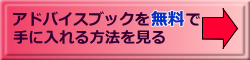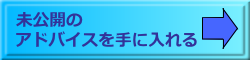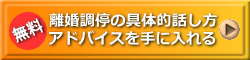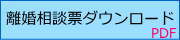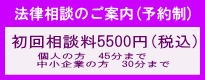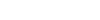ご予約・お問い合わせはTEL.0572-26-9852
〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
離婚調停で慰謝料・財産分与に争いがあるときの対処法
最終更新日:2024年6月2日

これさえ読めば離婚調停が自分でできる「裁判所HPより詳しい離婚調停解説」連載の第22回
- 財産分与と慰謝料ってどう違うのですか?
- 私が結婚前に貯めていた貯金も分けないといけないのですか?
- 自分の親に出してもらった住宅ローンの頭金を返してもらえますか?
- 住宅は相手が住むことになりますが,住宅ローンの保証人を抜いてもらうことができますか?
- 相手が,家を出て行くから「引越代」は支払え,と言いますが,払わないといけないですか?
- 慰謝料を1000万円請求されていますが,支払わないといけないですか?
- 相手が浮気したストレスで,病気になり,働けなくなりましたが,その分の生活費としてみてもらえますか?
離婚調停で慰謝料・財産分与といった離婚時の財産のやりとりについて争いがあるときには,どうしたらよいのでしょうか。
を,順に説明します。
財産分与に争いがあるとき
財産分与は,ひとことで言うと,「夫婦が協力して作った財産を分ける」ということです。
財産分与を考えるポイント
財産分与で,何を取得できるのかを決める上では,次の3点がポイントになります。
- 財産分与の対象となる財産
- 財産分与の割合
- 財産分与の対象財産を計算する時期
(1)何が財産分与の対象となる財産か
対象となる財産

- 主なもの
- 預金,現金,生命保険,学資保険,不動産(自宅),株式,出資金,退職金,貸付金などの債権,自動車,家財道具など,夫婦で協力して婚姻後に取得した財産は対象となります。
- 借金は?
- プラスの財産だけでなく,住宅ローン,学資ローンなど夫婦の共同生活のためにできた負債(借金)も財産分与の対象となります。
- 子供名義の預金・保険は?
- 子供名義の預金は,お年玉など子供自身が他の人からもらったものが預けられているのであれば,夫婦の財産分与の対象とならないでしょう。他方,給料から子供名義で積み立てていた場合には,財産分与の対象として捉えられることがあります。
子供にかけた学資保険も,夫婦で働いた給与から保険料をかけているのであれば,一般に財産分与の対象と考えられています。「被保険者」ではなく,「契約者」が誰になっているのかを確認して,夫婦の財産として計算しましょう。 - 自営業者の場合の事業用資産
- 相手方が,自営業者の場合,個人営業であれば,事業用の資産,負債も財産分与の対象となり得ます。他方,株式会社の代表取締役となっている場合,会社の財産は個人の財産とは別であり,原則として財産分与の対象とはなりません。
対象とならない財産

- 結婚前の財産
- 結婚前にあった預金,花嫁道具として持ってきた家財道具などは夫婦で共同して形成した財産ではありませんので,原則として財産分与の対象になりません。
結婚前から所有していた住宅・車でも,結婚後にそのローンを返していたような場合には,結婚後のローン支払い相当分は,例外的に財産分与の対象となります。 - 結婚後に相続・贈与を受けた財産
- 結婚中に,親から相続した遺産や贈与を受けた財産は,夫婦で共同して形成した財産ではありませんので,原則として財産分与の対象になりません。
- 結婚指輪・婚約指輪
- 結婚指輪も,財産分与の対象にはならず,離婚するからといって,法的に返すべき物ということにはなりません。
裁判所で使われる分かりにくい用語の説明

「夫婦共有財産」「特有財産」という用語が使われることがあります。
離婚調停でいう「夫婦共有財産」は,例えば,自宅の建物の名義が2分の1ずつの共有名義となっているような「夫婦共有名義となっている財産」に限らず,夫の単独名義になっているものであっても,婚姻後に購入し,夫婦の協力で取得できた財産分与の対象となる財産を広く含む言葉だと理解しておくと良いでしょう。
「特有財産」は,相続財産,結婚前の財産など,財産分与の対象とならない財産という程度の意味に理解しておけば良いでしょう。
(2)財産分与の割合
原則2分の1
財産分与は,結婚後に働いて稼いで形成した財産を合算して2で割って清算するというのが基本になります。「2分の1ルール」という言葉も使われるようになっています。
例外もある
医師,弁護士など専門的技術によって収入を得て夫婦の財産が形成されているような場合,例外的に財産分与の割合が,半々ではなく,専門職を有している配偶者に多くなることもあります。
(3)財産分与の対象となる期間
財産分与の対象財産の範囲を決める基準時は,「別居時」,「離婚成立時」などの考え方がありますが,夫婦としての共同生活が無くなった「別居時」とされることが多いです。
イメージとしては,婚姻時点を基準に夫婦の協力関係が終了する別居時点までに増やした財産を半々にします。婚姻時,100万円であった財産が離婚時(別居時)に1000万円となっていれば,差額の900万円が財産分与の対象になります。
財産分与額の概算

そのような財産の明細が明確になると,不動産などの財産の金銭評価の問題は残りますが,適切な財産分与の額が概算できます。それぞれの名義の財産を積み上げて,おおよその金額を計算してみましょう。
不動産などの評価方法
評価時点は,離婚時または別居時です。そのため,不動産の価値,自動車の価値(時価)は購入当初よりかなり下がっていることがあり得ます。
それぞれの取得すべき金額の計算
たとえば,別居時の夫名義の財産500万円,妻名義の財産200万円だとすると,合わせて,700万円となります。700万円÷2=350万円となり,それぞれ350万円ずつもらうことになります。
実際に相手に請求できる金額等
その際,妻は,自分名義の財産200万円を既に持っているので,350万円−200万円=150万円を夫に財産分与として請求できることになります。裁判になれば裁判官が分与する財産を決定することになりますが,話し合いによる解決をめざす離婚調停の場では,現金として請求しても良いですし,不動産,保険名義の変更などとして請求することもできます。
概算額をふまえた注意点
このような概算額から大きく離れた要求をしていると,多くの場合,調停委員,裁判所から,無理を言っていると思われてしまいます。
財産分与を有利に進めるための重点の置き方
財産分与を有利に進めるためのポイントは次の2つです。
- 相手名義の財産を明らかにすること
- 自分名義の財産の内,結婚前からの財産,相続・贈与により取得した財産を明らかにすること
結婚後に働いて稼いで形成した相手名義の財産が多いほど,結婚後に働いて形成した自分名義の財産が少ないほど良い(もらえる分が多くなる)ことになるからです。
相手名義の財産を明らかにする方法
見落としを無くす
財産を見落とさないように列挙する必要があります。
見落としやすいものとして,
- 掛捨てでない保険・共済
- 財形貯蓄
- 退職金・小規模企業共済
- 国民年金・厚生年金・旧共済年金以外の年金受給権
- 相手や親族が経営している会社の相手名義の株式
- 相手や親族が経営している会社に対する貸付金
- 結婚の時に抱えていた借金の減少
があります。
結婚の時に抱えていた住宅ローンや車のローンで,結婚生活でその物を使っているようなときは,借金減少そのものでなく,一般的に住宅・車の中に夫婦で形成した財産が残っているという考え方をすることになると思われます。つまり,その住宅,車の別居時での時価を財産として計算することになります。
退職金は,近い将来にもらえる場合でないと財産分与の対象とならないと言われています。理由は,遠い将来にもらえるかどうかは,不確実だからです。しかし,不確実性があるからと言って財産分与のときに全く考慮しないというのも不公平ですので,支給が時期が遠い将来になる退職金であっても挙げておいて良いと思います。
隠し財産を見つけ出す
預金,株式,生命保険等の金融財産が明らかにされていないときには,金融機関・支店を特定し,裁判所に申し立てて調査嘱託という方法で調査してもらいます。
どのように金融機関・支店を特定するかについては,同居期間中の記憶,手に入った証拠を精査して手がかりを見つけるしか無く,弁護士でも苦労しています。
別居する前に,相手方の預金,株式,保険などについて,どこにあるのか意識をしておくようにしましょう。
実質的に相手名義の財産と言えるものを見つけて説明する
たとえば,夫の親が自営業をしており,夫がそこに勤務しているような場合に,親に財産が貯まっているときには,実質的には相手名義の財産が増加していると評価できる場合があります。
相手の親と同居しており,親の生活費の負担をしているような場合も考えられます。
収入と支出から相手名義の財産を推計する方法の有効性について
非常に多く見られる主張に,「これだけ収入があったのだから,どこかにお金が残っているはずだ。相手方は隠している」というものがあります。
しかし,収入と支出から残っている「はず」の財産を計算しても,あまり考慮されません。支出を計算する際に,実際の支出額よりも小さく計算しがちで,計算結果があてにならないからです。相手の財産そのものを見つけ出すことを優先すべきです。それができなくても,財産が隠されていることを強く疑わせるような事実(短期間での多額の預金引出しなど)を見つけ出すべきです。
弁護士が使っている「財産分与を有利にする4大要素と重要ステップ」
弁護士が財産分与の争いの依頼を受けたときには,4つの大切な要素に気をつけています。そして,交渉や調停に臨む前のステップとして,ご依頼者のため,重要な1つの行為を行います。
今すぐ下のボタンをクリックし,ご確認ください。
結婚前からの財産,相続・贈与により取得した財産を明らかにする方法
自分の財産のうち,結婚前からの財産,相続・贈与により取得した財産を明らかにするには,資料を集めて,わかりやすく整理して説明することになります。
預金,保険については,まずは,結婚のときに既にその金額の預金,保険があったことの分かる資料(通帳の写し,保険証券の写しなど)を提出することになります。
その他の財産分与を有利に進めるための主張
財産形成への貢献度の主張
現在は,結婚後に働いて稼いで形成した財産を合算して2で割って清算するというのが基本ですが,例外もあります。
夫婦の協力関係が無い期間の存在や,折半するのがかえって不公平な事情があれば説明すべきです。
- 夫婦の協力関係が無かったような事情
-
- 家族を置いて家出していた
- 刑務所に入っていた
- 単身赴任中,一切の連絡が無かったなど
- 折半するのがかえって不公平な事情
-
- 医師・弁護士・画家・作家など結婚前から持っている特別の技能・資格が財産形成の原因である
- 経営手腕によって数千万円・億円の年収を生み出している
夫婦の協力関係により財産分与の対象外の財産の価値が維持・増加しているとの主張
- 不動産を相続した際に結婚後の貯金から相続税を支払った
- 結婚前から所有していた家を結婚後の貯金を用いて大規模修繕した
- 株式を所有し経営している会社の経営が結婚後に成功して会社の株式の価値が上昇した
といった事情があるときには,夫婦の協力関係の成果の一部を,一方が財産分与の対象とならない財産の中に先取りしていることになります。
このような事情を説明して,事情の考慮を求めることが有効な主張になります。
財産分与を有利にする効果の小さい主張
浪費の主張

相手が浪費したから財産が残っていない(だから,残っている財産は自分に与えられるべき)という主張は,あまり考慮されません。使ってしまって既に無い物は分けようがない,浪費の基準が不明確,浪費を食い止める努力が不十分で容認・放置していたという面があるためと思われます。そのため,浪費の主張の優先順位は低いことになります。
浪費の原因がギャンブルの場合,納得できないことも多いのですが,これらは,「離婚原因を作った」慰謝料の主張などと合わせて,主張していくことになります。
浮気(不倫・不貞行為)の主張
相手が浮気したのに,お金を渡さなければいけないのか,と言われる方が,よくいらっしゃいます。
確かに,気持ちとしてはとてもよく分かるのですが,財産分与は,夫婦で共同して作った財産の「清算」ですので,離婚原因がどちらにあるか,どちらが悪いのかには関係なく,請求できることになります。
生活費がこんなにかかるはずがないという相手の言い分への対応
家計を管理していなかった側(主に夫側)から,生活費がこんなにかかるはずがなく,内緒のへそくりがあるのではないかという指摘がなされることがよくあります。
家計を管理していた側からしてみると,大きな勘違いで,一生懸命やりくりしなきゃいけなかったのに,と思うようなことがあるでしょうが,こだわりが強く,その主張を無視していては話が進まないことがあるものです。
調停委員から,できる範囲での説明を求められることがあります。調停委員が相手の味方をしているというよりは,話を進めるために求めていることが多いものです。
自分の収入,相手の収入の平均と支出のおおまかな内訳(食費,医療費,学費,ガソリン代,光熱費など)をできる範囲で説明するようにしましょう。
管理していた通帳の履歴なども開示しなければ,話合いが進んでいかないことが多いので,調停での解決を希望する場合には,開示しても「納得してもらえない」という不安はあるでしょうが,履歴の開示も必要となるでしょう。
財産分与における住宅ローンの問題
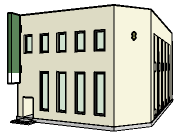
購入した自宅に住宅ローンが残っている場合の財産分与には,以下のような問題があります。別記事「住宅ローンが残っている離婚のチェックポイント」もご覧ください。
評価の方法の問題
基本的には,離婚時(別居時)の時価(時価が不明な場合は固定資産評価額が参考にされたりします)と住宅ローンの残高を比べます。
住宅ローン差引き後の評価がプラスとなる場合
例えば,「時価1500万円>ローン残高1000万円」であれば,1500万−1000万円=500万円が財産分与の対象となり,自宅を取得する方がしない方に半額の250万円を分与することになります(第三者に売却する場合もほぼ同じです)。
親が住宅資金を一部払ってくれた場合
どちらかの親が住宅購入資金の一部を負担(贈与)していたような場合には,その支払った金額も含めて,清算する割合を決めることになります。親から借金をして住宅を購入していたのであれば,まずは,親に返済する,という考え方になります。
住宅ローン残高が,住宅の評価よりも多い(マイナスとなる)場合
「時価1000万円<ローン残高1500万円」の場合は難しい問題です。
売却すれば,残ったローン残高500万円の負債を半々で負担することになります。
一方が取得して,住み続ける場合には,負債の方が多いので,不動産の価値としてはゼロとして計算することが多いです。残ったローンについては,住む方が,家賃代わりとしてローンも負担する,という考え方が多く採用されている,と感じます。
親が住宅資金を一部支払ってくれた場合
このときは,どちらかの親が住宅購入資金の一部を負担(贈与)していたような場合であっても,財産としての評価がゼロなので,その金額を返してもらうのは難しいです。親から「借金」をして住宅を購入していたと言えれば,通常の負債の財産分与と同じで,半々を借金として負担する,という考え方になります。通常は「借用書」などのやりとりはなく,この場合には,「借金」と考えることは難しくなります。
連帯債務者・保証人の問題
住宅には住まないから,住宅ローンの保証人を抜けたい,連帯債務者をやめたい,という話は,非常に多くあります。
しかし,結論としては,なかなか抜けられるものではありません。
なぜかといえば,保証人,連帯債務者としての契約は,住宅ローンを借りた金融機関との間のものだからです。仮に,相手は抜いて良い,と言っても,お金を貸してくれた銀行などが了解しなければ抜くことができないのです。
他の保証人を付けてくれれば,という話もありますが,金融機関の了解が得られ,保証人となることを引き受けてくれるような適任者を見つけられることは少ないのが現実です。もっとも,事案によっては,新たな保証人を付けないで抜くことができる場合もあるようですので,金融機関に自分で相談してみましょう。
財産分与の種類と言われているものの利用
財産分与には,次の3種類があると言われています。最高裁判所も,この3種類の財産分与を認めています。
- 清算的財産分与
- 結婚後に形成した財産の清算
もともと自分の持分であった財産を公平に払い戻してもらうイメージです。 - 扶養的財産分与
- 離婚により生活が困難となる(元)配偶者の扶養
生活困難となるので,その分も考えて,多めに財産分与をしてもらいたいというイメージです。 - 慰謝料的財産分与
- 離婚による精神的苦痛の賠償
相手のせいで離婚になったというときに,その苦痛の分も考えて,多めに財産分与してもらいたい,というイメージです。
しかし,離婚調停では,清算的財産分与だけを考えれば十分です。
離婚調停では慰謝料的財産分与を考える必要なし

慰謝料的財産分与が,慰謝料とは別に認められるわけではありません。また,慰謝料が認められるような状況でない限り,慰謝料的財産分与も認められません。
したがって,離婚調停では,精神的苦痛の賠償は全て慰謝料の争いとして交渉すれば十分です。
(離婚を先行させ,離婚後に財産分与・慰謝料を請求する場合には,財産分与請求の手続きと慰謝料請求の手続きが別の手続きになります。こうした場合は,財産分与請求の手続きで「慰謝料的財産分与」を求めて1個の手続きで解決することに意味があります。)
離婚調停では扶養的財産分与も考える必要なし
離婚によって夫婦は他人となるので,その後は,扶養してもらえないのが原則です。

その原則の例外として,離婚後も,一定の範囲で扶養を考えるのが,扶養的財産分与です。そのため,通常は,離婚後の生活費を負担させないと,あまりにかわいそう,と考えられるような特殊な場合にしか認められていません。
例外的な場合として,たとえば,家を出て愛人と生活している夫と,高齢の専業主婦の妻の離婚のパターンが考えられます。
扶養的財産分与をとりまく現代社会の実情
しかし,平成19年4月に年金分割制度が開始され,結婚後に形成した年金の権利を夫婦平等に分割することができるようになりました。年金が受け取れる年齢(高齢主婦)であれば,年金分割をすれば足りるので,夫が受け取った厚生年金・旧共済年金の一部を,扶養的財産分与として離婚した妻に渡すという必要はなくなりました。
また,昔は,結婚後に形成した財産を清算的財産分与で分けるとき,専業主婦に認められる割合が低いのが通常でした。しかし,現在は,特殊事情がない限り,清算的財産分与は2分の1ずつというのが通常です。
昔と違って,女性もパートなどに働きに出る時代になっており,離婚後に収入が全く見込めないと言える場合も少なくなっています。
こうした中で,清算的財産分与に加えて,さらに離婚後の生活費を負担させるという例外的取扱をしてまで救うべきと考えられる場面が減っています。
つまり,ほとんどの夫婦にとって,扶養的財産分与は関係がないのです。
婚姻に伴い退職した場合の不利益回復の手段

結婚を機に退職して専業主婦となったため,今後働いて生活するための収入を得るのが困難になった場合に,(清算的財産分与では足らないので)扶養的財産分与を考えることがあります。
しかし,これは,「扶養的財産分与」はなく,「慰謝料を増額する根拠」として説明した方が分かりやすいと思います。慰謝料を請求する際,「結婚を機に正社員を退職したのに,離婚せざるをえなくなり,少ない収入・無収入の状態から再出発しなければならない精神的苦痛」のような苦痛も理由に挙げることができます。例外的な取扱となっている扶養的財産分与に挑戦していくよりも,慰謝料を増額すべき理由で説明する方が,正当性を示しやすいものです。
調停での解決での困難性
扶養的財産分与が認められるような場面でも,扶養的財産分与の金額や計算方法の基準が定まっていません。基準がないために,一応,月額○万円の○年分という計算式を示すことはできても,それが正当であると調停委員に納得してもらうのは困難です。

裁判官が結論を下す裁判・審判手続きと異なり,合意による解決をめざす離婚調停の手続きでは,「慰謝料でも財産分与でも理由は何でもいいから○○万円欲しい」「慰謝料と清算的財産分与の相場で計算した金額では少なくて不当だから○○万円加算されるべきだ」と言って交渉するのと,あまり変わらないことになります。扶養的財産分与という「言葉」は使っても,説得的な計算式が示せないことが多いので,あまり意味がないことになります。
裁判事例においても,「扶養的財産分与」が認められている事例はほとんどありません。最近の事例として認められているものでは,妻が清算的財産分与だけではあまりに少なく,他方で,夫は固有資産,資力(収入)があるような場合に,住宅ローンが残っている自宅に住めなくなるのはかわいそうだから,「扶養的財産分与」として,しばらくの間住んでも良い権利(使用借権,賃借権)などを認めているようなものが,「特殊」な事例としてあります。
慰謝料・清算的財産分与・年金分割では生活できないときは?
清算的財産分与と慰謝料相場を知り,これを受け取り,年金分割を受けても離婚後の生活の目途が立たないというときには,まずは,弁護士に相談して,本当に離婚していいのか?など,方針を練り直すことをお勧めします。
しかし離婚調停でも,請求する「理由付け」に有効
このように「扶養的財産分与」の交渉に意味がないとは言っても,小さい子供連れの場合,すぐに働くのはやはり困難,離婚後当面の生活費を負担して欲しい,出て行くのであれば,引越代を出してほしいという場合があります。
そのとき,本音の説明を抑えて,その分の金額を加算した慰謝料を請求したり,理由はともかく,これらの支払をしてくれなければ,離婚しない,と交渉することも可能です。ただ,このような交渉方法は,調停委員の共感を得られにくいという問題があります。

離婚後すぐに生活に困るような事態を避けたい,離婚に伴う引越費用がかかるというのは,本音の方が共感を得られやすい事情です。また,感情面だけでなく,「扶養的財産分与」という裁判所でも認められている「法律上の理由付け」があると,更に,調停委員の共感を得られやすくなります。そのときに,「扶養的財産分与」という考え方で支払ってほしい,という理由付けが有効になります。
つまり,「扶養的財産分与」を実際に計算して請求するというのは難しいのですが,離婚による引越代などの出費,生活費の減少を考慮してほしい場合に,その「法律上の理由付け」として「扶養的財産分与」を理由とすることになります。
また,相手方も「慰謝料請求」という形で請求されると,「俺は悪いことしていない。慰謝料は認めたくない」という気持ちから,抵抗されることも多いのですが,「生活が大変なので,扶養的なものとしてお願いしたい」と説明する方が抵抗されにくいことが多いと感じます。
離婚調停を弁護士に依頼しない方へ
離婚調停では,調停委員への「話し方」が大事です。
あなたが弁護士に依頼をしないのであれば,あなたは,自分自身で調停委員に話をすることになります。
現在,多治見ききょう法律事務所では,具体的な「話し方」のアドバイスブックを無料で欲しい方を募集しています。
今すぐ下のボタンをクリックし,アドバイスブックを手に入れてください。
そして,離婚調停であなたが話をするときに利用してください。
慰謝料に争いがあるとき
慰謝料は,夫婦関係の破綻に責任のある側(悪い方)が,責任のない側に対し,精神的苦痛の賠償として支払う金銭です。したがって,この意味では双方が「性格の不一致」で離婚しようとする場合には,裁判上慰謝料が発生しない,ということがあり得ます。
しかし,離婚調停においては,そういう意味での慰謝料の請求ができない場合,もしくは支払わなくて良い場合であっても,支払って解決されていることも多いものです。これは,なぜでしょうか?
離婚裁判の慰謝料と離婚調停の慰謝料の微妙な違い
- 離婚裁判(離婚訴訟)では,裁判官が証拠に基づいて事実を認定し,慰謝料を決定します。離婚調停では,事実認定をしません。そのため,例えば,相手が不倫(不貞行為)を認めていない場合など,慰謝料が発生するかどうかをはっきりさせないまま手続きが進められることがあります。
- 離婚裁判(離婚訴訟)では,慰謝料は相手が支払うお金を持っているかどうかに関係なく,決められます。離婚調停では,相手がお金を持っていない場合,合意が難しくなります。
- 離婚裁判(離婚訴訟)では,終了までに時間がかかることが予定されています。離婚調停では,早く解決するため,もしくは,早急に生活費(婚姻費用)の分担を減らすため,裁判であれば慰謝料を支払う必要が無い場合であっても支払うという選択があり得ます。
このようなことから,離婚調停の慰謝料は,離婚裁判の慰謝料と微妙な違いが生じてきます。この離婚調停の特徴を活かした,慰謝料の主張ができるように心がけましょう。また,裁判では,裁判官が慰謝料を認めるかどうか,その金額をいくらにするかを全て決めてしまいますが,離婚調停では,お互い譲り合って決められる手続きです。裁判にならずに早めに解決するため,どう考えたら自分が譲れそうか,相手に譲ってもらえそうか,相手方がどのような気持ち,どのような生活状況なのかを想像することも大切です。
精神的苦痛の賠償(補填)としての適正額を意識する
慰謝料には客観的な基準は無く,離婚裁判(離婚訴訟)の裁判官のように決める人がいない離婚調停では,「適正な慰謝料額」を前提にした話が容易ではありません。もっとも,裁判での相場観と自分の主張が合っているのであれば,これを調停委員に伝え,主張の正当性を理解してもらうのが有用です。相場について詳しくは,連載第10回「失敗しない離婚調停申立書・付属書類の書き方」をご覧ください。
賠償とは違う「慰謝料」の理由も考える
離婚調停は,法律以外も考慮して適正な解決をめざす手続きですから,法律上慰謝料を支払うべき場合かどうかを深く吟味せず,離婚条件を少しでも公平に近づけるという適正さための金銭の支払が話合いの対象になることがあります。これをふまえて,法律上「慰謝料」が認められるか,という観点を少し離れて,支払って解決しても良いか,解決すべきかを考えてみましょう。
自分と相手の「慰謝料」へのこだわりが何であるのか(お金自体なのか,非を形にすることなのか,報復感情なのか)がわかっていないと,離婚調停がかみ合いません。1つではないこともありますが,ウェイトがあるはずですから,ウェイトの大きいものを重点的に解決していくことになります。
1 悪かったこと(非があること)を形にする手段
離婚調停では,夫婦のどちらにどの程度の非があったのかが,慰謝料の形でしか残りません。相手に非があったことをはっきりとさせたい,相手に非を認めさせたい,相手に謝ってもらいたい,という希望・こだわりが,離婚調停時の慰謝料の話合いに影響します。
自分にそのような気持ちがあるのであれば,そういう気持ちを調停委員に説得的に伝えるようにしましょう。場合によっては,謝罪の文言を調停調書に入れてもらうことで,金額を下げる,という方向もあるかもしれません。
反対の立場では,非を認めたくない,自分には非がないということをはっきりさせたいという希望が,慰謝料の話合いに影響します。その場合には,支払うとしても,「慰謝料」という文言ではなく,「解決金」として支払いたい,などの気持ちを調停委員に伝えるようにしましょう。
2 報復感情の満足の手段
自分が苦しんだから,今後の慰謝料支払で相手に苦労をさせたい,という報復感情が慰謝料の話合いに影響することがあります。裁判では認められにくい主張ですが,調停での解決のために譲ることができそうか,検討してみましょう。
3 早く確実に離婚するための手切れ金
離婚裁判(離婚訴訟)よりも前の段階である離婚調停では,離婚裁判で強制的に離婚を実現するまでに先が長いことになります。離婚が実現されるまでの金銭的負担(婚姻費用,弁護士費用等)も生じます。離婚裁判(離婚訴訟)になった後以上に,手切れ金としてお金を渡してでも,早く確実に離婚した方が良いという判断がなされやすくなります。最終的にどうした方が,時間,お金が得になりそうか,という観点で譲れるかどうか,検討してみましょう。
4 離婚を公平にする手段
結婚あるいは出産のときに正社員を辞めたなどの事情により,離婚後の不利益が偏ることがあります。家を出て行く方に引っ越し代の負担をすることなども,これに当たるでしょう。養育費,財産分与でも考慮され得ることですが,幼い子がいる状態で働くこと,それまで無職だった方が年配になってから働くことは困難であること,などからも「慰謝料」として金銭を負担することが考慮されても良いでしょう。
「慰謝料」という言葉にこだわるべきかどうかを考える

「慰謝料」ではなく,「解決金」という名称で金銭の支払いを合意するという方法があります。どちらも大きく痛むことなく,まあまあの納得が得られる解決策です。
非を形にしたいという希望は,ご本人の考えの持ち方次第で,満足感が異なってきます。
もっとも,不貞行為が絡む場合,不貞に関係する慰謝料は,不貞行為の相手(不倫相手)との連帯責任となります。慰謝料を支払ったのか,慰謝料が支払われていないのかにより,不倫相手に慰謝料の支払責任が残るかどうかに違いが生じます。こうした場合には,解釈に疑義を残さない解決をめざすべきことになります。
不可能な要求を見極める

財産分与が残っている物を分けるものであるのに対し,慰謝料は残っているかどうかに関わらず金銭の支払いをする性質のものですから,請求が適正であっても実際の支払は不可能という可能性があります。
一括払いが無理なら分割払いという選択肢もありうるのですが,分割払いも,収入から生活費を差し引いた残りの中から払うしかありませんので,収入が少ないとき,別途養育費・住宅ローンなどの支払いがあるときには,支払に充てられるようなお金が残らないことがあります。
支払を求められている立場の場合は,自分の財産の状況や収支状況を理解しておき,不可能な要求に対しては不可能であることを即答できるようにしておくべきです。
支払を求めるときには,不可能な要求をぶつけても成果にもつながりません。無駄な時間をかけるだけになります。相手の計算能力が低いために合意に至ることがあっても,すぐに払えなくなりますから,勝ち取った調停条項は無駄になります。
現実を冷静に見つめて,何が可能で何が不可能なのかを,見極めておくべきです。
財産分与・慰謝料にこだわることで失うものとのバランスを忘れずに
財産分与・慰謝料以外の金銭面での問題
お金に色はありません。財産分与・慰謝料で得られる「お金」は,働く,福祉的な給付を受けるなど,別の手段でも手に入ることのあるものです。
- 離婚が成立すれば,児童扶養手当などの福祉的な金銭給付を受けられることがあります。
- 離婚調停に費やす時間が無くなれば,その時間に働いて給料が得られるかもしれません。
- 離婚が成立すると,子育て・教育の支援制度のうち,親権者(保護者)の所得・資産額により制度利用の可否・支援額・自己負担額が判断されるものについて,相手の所得・資産額が除外されることにより,利用できるようになったり,支援額が増えたり,自己負担額が減ったりすることがあります。例えば,次のものです。
- 保育所の保育料がかかる0〜2歳児の子 保育料
- 高校生の子 高等学校等就学支援金制度(返還不要の授業料支援制度)
- 大学生・専門学校生など 高等教育の就学支援制度(授業料減免・給付型奨学金)
- また,離婚裁判(離婚訴訟)をするとなれば,弁護士の費用などの支出が生じます。
慰謝料へのこだわりが本当に金銭的に得になるのかを見極める必要があります。しかも,慰謝料は,相手に支払能力が無いために実際に支払ってもらえない場合があるのに対し,福祉的な給付は,条件さえ満たせば確実に得られます。
福祉的な金銭給付や保育所利用料についての詳細は,別記事「別居後離婚後の児童手当・児童扶養手当・保育料等の扱い」をご覧ください。
金銭面以外の損失
お金以外にも,離婚が成立するまで,精神的な負担,時間の負担が続きます。離婚が成立するまで他の人と婚姻できないという負担が伴います。これらの負担はお金と比較しづらいのですが,意識しておく必要があります。
財産分与・慰謝料で損をしてでも他で得を取るという選択肢も検討しましょう。
財産分与・慰謝料Q&A
- (財産の使い方の合意が財産分与に影響するか)
Q1 婚姻期間中は私が家計を引き受け,夫のお金遣いが荒かったので,将来子供が困らないようにと思い,婚姻期間中の私のパート収入から預金してきました。その預金も財産分与の対象に入るのでしょうか?(夫から,婚姻期間中の私の預金を半分よこせと言ってきています。)
Q2 私はフルタイムで働き,夫とほぼ同等の収入があります。結婚からしばらくは小遣い制にしていましたが,お金のことで頻繁にけんかがあったので,この10年近くは子供・家族分の生活費を割り勘で出して,残りは,各自で管理し,老後のことも各自で貯金して備えるように言ってきました。
ですから,夫がどんな買い物をしてこようと追及せずにきました。
私はいつか離婚したときのためにも地道に貯金してきたのですが,もし私が離婚調停を起こすと,貯金を財産分与で分けることになるのでしょうか? - A 結論から言いますと,Q1,Q2のいずれのケースも,ご質問者の預貯金は財産分与の対象となるのが一般的です。なぜかというと,ほとんど利用されていないのですが,民法上,夫婦財産契約という制度があるため,この手続きで決めておかない限り,原則として,婚姻してから形成した財産は,財産分与の対象となるものとして,扱っているからです。
こうしたルールにより,専業主婦であっても,夫の収入によってできた預金・財産についても,妻の家計管理や家事・育児等を含む夫婦共同生活の成果として得られたものとして,財産分与してもらえる,ということになります。
しかし,ご質問のケースでは,一生懸命預貯金を貯めてきたご質問者にとって,不公平に思われることも多いと思います。
この点,Q2のケースでは,財産分与の対象とならない可能性もあると思われます。裁判例においても,婚姻前からそれぞれが作家,画家として活動しており,婚姻後もそれぞれが各自の収入,預貯金を管理し,それぞれが必要な時に夫婦の生活費用を支出するという形態をとっていたことが認められ,一方が収入を管理するという形態,あるいは夫婦共通の財布というものがない事案では,婚姻中から,それぞれの名義の預貯金,著作物の著作権についてはそれぞれの名義人に帰属する旨の合意があったと解するのが相当であり,各個人名義の預貯金,著作権は清算的財産分与の対象とならない,という判断をされたものがあります。
そのため,Q2のケースで,ご夫婦で「残ったそれぞれ名義の預貯金」はそれぞれのものとする,という合意まであった,といえれば,これを前提に清算する,つまり,ご相談者名義の預金は夫に渡さなくても良い,という考え方もあると思われます。収入も夫とほぼ同程度,という点も清算的要素が少ない根拠となると思われます。(もっとも,途中で財産の管理方法を変更しているので,少なくとも,この点の清算は必要になると思います。)
他方,Q1のケースでは,「浪費」「お金遣いが荒い」というのは,どのレベルを超えると「浪費」「お金遣いが荒い」と言えるかの基準が難しいため,ご質問者名義の「貯金が残った」のが全て質問者のおかげであると言い切ることが難しいです。一切清算しない,というのは難しいケースと思われます。収入の主な担い手が夫とうかがわれる点も,清算する方向に働きやすいと思われます。
もっとも,財産分与は,家庭裁判所が,「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」とされているため,夫の浪費の程度によっては,清算すべき額を低くする根拠とはなり得ます。その他にも,夫婦の共同生活における家事・育児を全く負担せず,財産を維持するための貢献度が低いといえるような事情があれば,これも「一切の事情」として裁判所が分与すべき額の判断をすると言えます。
もっと昔には,専業主婦である妻の貢献度は低いと考えられていたので,専業主婦の財産分与の割合が2〜3割程度の時代もあったようです。現在では,家事・育児の従事による財産形成への寄与(内助の功)が重視されて,原則として2分の1の割合が認められています。
しかし,さらに進んで考えると,家事労働の対価は,夫の収入で形成された財産の半分が適切なのでしょうか?夫の収入によっても違ってくるのではないかと思います。妻も働いていることが一般的になってきた現在,夫が何ら家事・育児を負担していない場合(内助の功があると言えないような場合)に,妻が働いて形成した財産を夫に分与する必要はあるのでしょうか?
妻の不満は,夫の仕事は,私が家事や育児を負担しているからやっていけているけれど,私の仕事は,夫が家事や育児を助けてくれているからできているわけではない,という気持ちにあるのではないでしょうか?(家事や育児が今のようにできなくなるなら,仕事はやめて欲しい,と夫から言われているようなケースもありますね。)
以前話題となった「逃げ恥(逃げるは恥だが役に立つ)」のドラマは,「家事労働」の適切な対価について,考えさせられます。「育児労働」「介護労働」の対価についても,同様の問題があると思います……
外国人との間の婚姻で,当然のように,相手方から最初に夫婦財産契約をすると言われたお話をお聞きすることもあります。
夫婦財産契約は,婚姻前に契約しておくこと,登記しておくことなどの条件が厳格で使いにくい制度ではありますが,少なくとも「契約」として,書面で,離婚の際の財産の分け方を当事者間で決めておくと,離婚時の「財産分与」の方法・割合を裁判所が判断する際にも役に立ちそうです。
もっとも,婚姻後に様々な事情が変化するので,常に家事・就業・育児などの負担割合は変わり得ます。そのため,「契約」したとおり,離婚時に清算するのが公平とは言えなくなる場合もあり得ます。そういった事情も「一切の事情」として,財産分与の対象とするかどうか,その割合(額)をどうするかに影響してきます。
ご質問のケースのように,婚姻期間中に形成された自分名義の預金について,離婚時には清算すべき「財産分与」の対象とし,2分の1の割合で夫に分ける,という原則的な今の取扱方法がおかしい,と感じる場合には(実際には,とても難しいのですが……)適宜,合意を書面化して残しておくこと,少なくとも文書でその意思を伝えておくこと,などを考える必要があると思います。 - (長期別居中の夫に財産を持っていかれるのか)
Q 子供を3人産み2人は大学を卒業し社会人です。残念ながら3人目の子供は幼くして亡くなりました。夫は気が短く,反論すると平手で殴ることがしばしばありました。別居を決意したのは,娘が亡くなったことを,お前のせいだとの暴言を言われ,精神的に参ったからです。今から15年前に,別居し,家庭裁判所で調停を行いましたが不成立に終わりました。夫はあまり働いてくれず,家計はいつも苦しい状況で,私が働いて生活してきました。別居後も,夫からは生活費をもらわず,一人で子供たちを育ててきました。
最近になって,離婚しないと私の財産を夫に持っていかれるかもしれない,老後の夫の面倒を看なければいけないかもしれないとの話をききましたが,どうなのでしょうか?
そのため,最近,再度話をしましたが,離婚に応じてくれません。
このような状況の場合,どうしたらいいでしょうか? - A この場合,別居後に得た収入,財産は夫婦の協力によって得た物ではないので,離婚する場合に財産分与の対象とならないのが原則です。つまり,離婚時に分ける財産にはなりません。しかし,15年前の別居当時にはどれだけ財産があったのか,区別できるようにしておく必要があります。
夫の看護については,民法上,「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」とされているので,夫が入院したり,生活保護の申請をするような場合には,法的には看護や,生活費の援助をする必要が出てきます。あなたに,無理矢理,夫の看護させることはできませんが,「法的な」義務を負っている状態ではあるので,金銭負担を請求される可能性があります。万一,あなたが亡くなれば,夫は相続人としてあなたの遺産を相続する権利もあります。その意味で,あなたの財産を渡したくないのであれば,離婚手続きを進めた方がよいでしょう。
手続きは,まず,離婚調停を行うことになります。到底話合いでの解決は難しいと思われるでしょうが,法律上,離婚手続きでは,裁判の前に調停をすることになっています(調停前置主義)。以前に離婚調停をしているということですが,15年も前のため,大きく事情も変更していることから,再度調停をしなければ,裁判をすることは難しいでしょう。形式的になるかも知れませんが,まずは,早急に離婚の調停申立をしましょう。そして,調停でやはり,話合いによる解決ができない場合には,早めに不成立にしてもらい,裁判手続きに進むのが良いでしょう。もしかしたら,不成立になったら,裁判に進む意思を明確に告げることで,離婚調停での話合いが進んでいくかも知れません。
私が代理人となった事案では,別居後40年以上経ってから離婚調停をしたけれど,合意ができず,裁判になったものもあります。裁判になる場合には,専門的知識が必須となりますので,弁護士に依頼すべきだと思います。 - (夫側からの財産分与請求ができるか)
Q 別居前には,生活費を夫婦で半分ずつ折半で出し合っていました。妻は,正社員でないとボーナスをもらえず,正社員になるためには夜勤もしなければならなかったため,妻が夜勤のとき,私は会社に無理を言って休みを取り,子守りをしていました。私の給料は休んだ分だけ少なく,妻が正社員でいられたのは私のおかげであり,私も貢献していると言えると思うのですが,財産分与は貰える権利はあるのでしょうか? - A 財産分与は,夫婦の協力により築いた財産を清算するという「考え方」なので,夫,妻のいずれの名義の財産であっても,それがご夫婦の協力で形成された財産と言えれば,清算の対象となります。
ですから,妻側だけが財産分与請求ができ,夫側からの財産分与請求ができないということにはなりません。
妻名義の財産(預金など)でも,この夫婦の協力によって形成された財産と言え,妻名義の財産の方が多いのであれば,男性であるご質問者からの財産分与の請求は可能ということになります。 - (夫婦共有財産の範囲)
Q 現在居住の不動産は,籍を入れる前に,親が出してくれたお金とローンで購入したものです。これは,共有の財産になりますか? - A 籍を入れる前に購入したという点は,財産分与の対象とならない一つの要素となります。しかし,この住居が夫婦で生活するために購入した財産で,住宅ローンの返済も夫婦で協力して生活しながら行ってきたとすれば,財産分与の対象となる夫婦共有財産と言える可能性の方が高いでしょう。
親御さんが出された分は,具体的な分与割合において考慮することになります。この場合,2分の1ずつ分けるということにはならないでしょう。
このケースで,できるだけ有利に計算をして,提示する方法については,「財産分与攻略ノート」に書いていますので,参考にしてください。 - (夫,妻の財産調査)
Q 地方銀行の預金は調査されますか?弁護士さんに調査の権限はありますか? - A 調べることは可能です。具体的には,相手方が,裁判所に申し立て,裁判所から金融機関等に対して,調査を行ってもらいます。
これを調査嘱託(ちょうさしょくたく)と言います。
もっとも,離婚調停の間は,裁判所に申立てをしても,裁判所はその必要性を認めず,行ってくれないこともあります。なぜかというと,そこまで争うのであれば,裁判をした方がよい,という考え方があるからです。
その他には,ご質問のように,弁護士が調査する,ということもあります。具体的には,相手方が依頼している弁護士が,弁護士会を通じ,金融機関などに預貯金残高などを照会するという方法で行います。
ただ,裁判所の調査嘱託に対しては,回答してくる金融機関が通常ですが,この弁護士会照会に対して,金融機関が回答をしないこともあります。
・・・こう聞くと,調停の間であれば,自分名義の預金口座もばれない可能性があるから,隠しておこう・・・と思われるでしょうか?
確かに,戦略的にそういう方法を取る方もいらっしゃいます。
けれど,弁護士木下の場合は,少なくとも預金口座があるのに,「ない」と明らかな嘘をつく方法はおススメしていません。
なぜかというと,裁判になってからの事案ではありますが,この嘘が発覚したために,著しく不利になった方の実例もあったからです。
その方では,実際に何度も裁判所や相手方から,他に財産はないか確認され,「ない」と回答されていたのですが,調査嘱託をした結果,少なくない財産が発覚した,というものでした。
それ以降,その方が主張していたDV,モラハラがあったという事実なども,裁判所は殆ど信用してくれなくなってしまったのです。
1つの嘘が,裁判所に「この人の言うことは信用できない」と思わせてしまうことのないよう,注意して対応することが重要です。嘘をつかないという姿勢の方が自分に誇りも持てると感じますし,裁判所に対する信用,誠実な態度を表すためにも
嘘をつくことは避けるべき,と考えています。もっとも・・・
いつ財産を開示するのかは難しい問題だと思っています。
自分は開示したのに,相手は開示してくれなかったらやはり損では!?と思うこともあると思います。
いつ開示すべきか,そのタイミングや提出方法は,具体的な事例,場面,相手方の対応などに応じて,進めて行くのが良いと思います。
このあたりは,個別に弁護士に相談しながら,進めてもらえたらと思っています。
(弁護士 木下貴子)
動画解説
弁護士木下貴子が,このページ「離婚調停で慰謝料・財産分与に争いがあるときの対処法」をYouTubeでお伝えしています。
真剣に離婚調停の準備をしているあなたに,お願いがあります
弁護士を付けないで離婚調停中の方に,私,木下貴子からのお願いです。
もっと具体的な離婚調停のアドバイスにご興味はおありですか?
もしご興味がおありならば,次のボタンを押して,アドバイスブックのダウンロードページに行き,どれほど簡単に離婚調停で話せるようになるか試していただけないでしょうか? アドバイスブックでは,ホームページ未公開の具体的アドバイスを掲載しています。
弁護士を付けずに離婚調停をする方に役に立つよう作成したつもりですが,本当に役に立つものであるかを確認したいと考えています。ダウンロードは無料ですので,一切費用はかかりません。
そして,ご感想やご意見をいただけるようであれば,お知らせください。
ご感想やご意見の回答義務はありません。ご感想やご意見の有無自体も,私にとって,参考になる情報です。